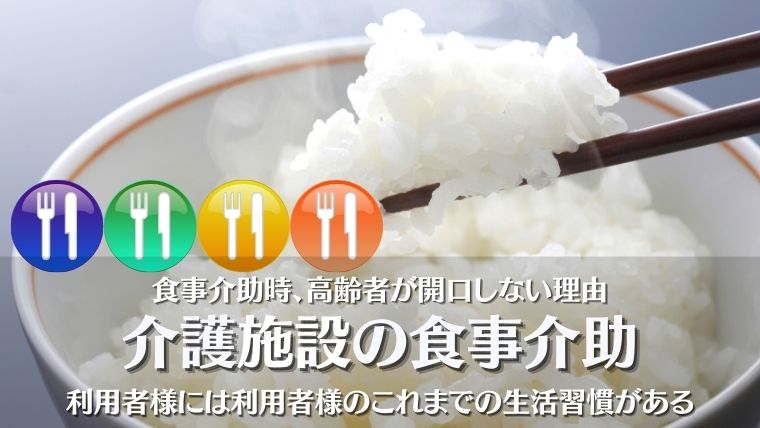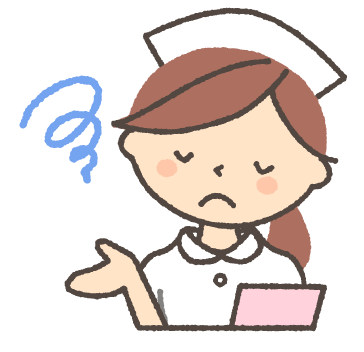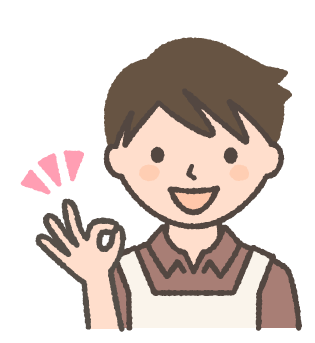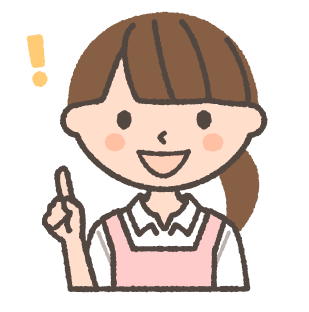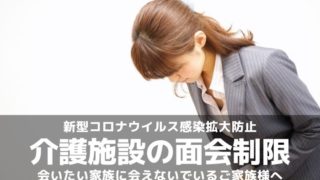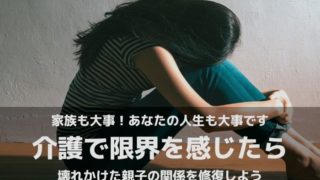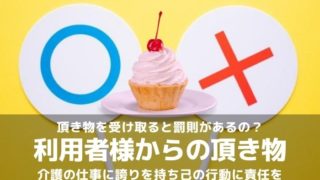【食事介助】【入浴介助】【排泄介助】とは三大介護ともいわれ介護を行う上で、欠かせない身体介護です。
今回は【食事介助】の中で、誰もが一度は経験があると思いますが、食事介助時、利用者様の開口が悪くなる理由と対策についてを記事にします。
新人職員のりょうこさんと同じように、食事介助時、思うように業務が進まず困っていらっしゃる方にお読みいただくことで、何かしらの気付きやヒントがご提供できればと思います。
高齢者がお食事時、開口が悪くなる理由
「1時間、Aさんだけの食事介助に徹して下さい」であれば、悩むこともないでしょう。
りょうこさんが働いている施設には、各フロアには、30名以上のお客様がいらっしゃいます。
介助が必要な利用者様はAさんだけではないから焦るのです。


- 開口が悪くなる利用者様の声に耳を傾けてください
- 食事介助を行う上で大切なこと・ポイント
- 食事介助時の声掛けを控えた方が良い理由
- 昼食時、バタバタしてしまうのは何故なんでしょう
上記についてを記事にします
食事介助:口を開けたくない理由
食事介助を行う際、高齢者様の開口が悪くなる理由について考えてみましょう。お読みいただくと実に様々な理由があることが解かると思います。
私たちも、口内炎がひとつできただけでも食事が美味しくなかったり、染みて痛いことから食欲が減退することがありますよね。


Q&Aの答えは【対応方法】で解説します。ご利用者様の声と、その内容がどのようなことなのかをお伝えします。
質問の内容を更に解りやすく説明して、何が問題なのかを明記します。
Qの右端の∨をタップしてくださいね。
高齢者の食事介助/お食事の一口量
早く食事介助を進めようと1口の量が多くないですか?立て続けに介助を続けると、飲み込めていないお食事がどんどん口腔内に貯留します。
【対応方法】食事介助時の一口量の目安とポイント
食事の一口量ですが、多過ぎると一度で飲み込めなかったり、逆に少な過ぎても同様にうまく嚥下(飲み込み)が出来ません。
ティースプーンで軽く1杯程度が適切と言われています。


一口量は個人差がありますので目安としてください。また、一口量は同量、一定にしてください。
職員のペースで一口量を変えてしまうことで利用者様の摂取ペースが崩れてしまいます。どのようなことかと申しますと誤嚥のリスクが高くなります。
食事介助中に利用者様を観察するポイント
食事介助中、周りのご利用者様にも目や気を配ることは大切ですが、目の前のご利用者様の摂取の様子を観察しましょう。
【対応方法】食事が嚥下(飲み込み)できているかの確認の方法
具体的に、利用者様の喉元を観察し嚥下(飲み込み)の確認をしましょう。


実際に鏡を使って食事を嚥下(ごっくんと飲み込む)時、喉元がどのような動きをするのか確認してみましょう。
鏡を見ながら、口腔内に唾液を溜めて、飲み込んでみてください。喉元が動くのが解ると思いますが、実際に喉元に触れると更に解りやすいと思います。
口腔内に入っている咀嚼(そしゃく・噛み砕く)中の食事は一度で飲み込まれず、口腔内のお食事の半分程度を飲み込まれたあと、残りの半分を飲み込まれることもあります。
食事用のエプロンを使用されていると喉元が隠れて見えないことも。必要であれば喉元が見えるようにずらす、若しくは透明の使い捨てエプロンもお勧めです。
施設のエプロンは無駄に大きい
食事が全介助の利用者様のエプロンは小さいもので十分です。
食べこぼしや吐き出されることもありますが、職員が目の前にいるので対応できます。エプロンはご利用者様毎に適切なものを選びましょう。
食事介助を行う前に適切なお声掛けを
一人の職員が複数のご利用者様の食事介助をすることも、場合によってはありますが、お食事は利用者様の目の前に配膳しましょう。食事の形態が細かく刻まれていると、見た目だけでは肉なのか魚なのかも解らないことがあります。


【対応方法】食事は利用者様の楽しみのひとつです
忙しいからと職員が立った状態での食事介助は、利用者様にとっては顎が上がった状態で介助を受けることになります。誤嚥のリスクが高くなります。
ひとりで2人、3人の食事介助をする際に、職員の周りにお客様の食事を並べて、お客様には食事が見えていない状態はNG。お客様の食事の介助をするということを忘れないでください。
上記、敢えて情けなくなることを書きました。お客様のお食事の介助を行う筈なのに、職員の周りに利用者様を集めて職員が同時に介助を行う。
嘘のような本当の話です。あってはならないことなので、実際にあったことを書かせていただいています。私が新人職員の頃に勤務していた職場では普通に行われていました。
当然ですが、利用者様の食事です。介助者は利用者様の右(利き手側)横から食事介助を行います。
食事を詰まらせて呼吸停止に至ることもあります。食事介助はマンツーマンでの介助が基本ですが、多くても2名に留めましょう。
事故が起きてしまってからでは遅いです。自分が行った介助で後悔することがないように、命に関わる仕事に携わっていることを今一度認識して、日々の業務にあたりましょう。


現場職員の声
「理想と現実は違う」「無理」という現場職員の意見もあると思います。職員の配置、休憩時間の調整、食事の提供時間を調整することで、それは出来ます。食事介助は介護職員だけではなく、看護師の業務でもあります。
「無理です。できません。」と否定するのではなく、○は出来ないけれど、△なら出来る等、どうしたら出来るようになるのかをフロアやユニットで行われる会議で話し合ってみましょう。
また、現場が回らない時はもちろんあります。生活相談員、ケアマネジャーにも遠慮なく声を掛けてください。
[the_ad id=”2304″]
食事時のお声掛けで留意すべき点
食事介助に入る際、どのような説明を行っていますか?無言で介助に入っていませんか?
先日、無言で食事介助を行う職員を見掛けました。職員に、何故無言で介助を始めたのか聞きますと、「食事中の声掛けは控えるように言われているから」と返事がありました。
確かに、食事中のご利用者様への無闇なお声掛けは、後述しますが誤嚥(食事や唾液が誤って食道ではなく気管に入ってしまうこと)のリスクがあるため、控えるように言われています。
ですが、お食事前については適切なお声掛けは必須です。
介助時の留意点を新人職員に指導の際は、単に食事中はNGですとか食前はOKだけではなく、何故、食事中のお声掛けを控えなければいけないのかの理由も説明しましょう。
配膳時に大切なことは、食事札の名前と利用者様の確認からはじまります。ご利用者様それぞれのお食事の形態(常食、刻み食、ソフト食、ミキサー食等)が表記されていますが、内容に間違えがないかを確認しましょう。


単に食事を間違えて配膳したから、新しい食事を提供すれば良いというわけではありません。配膳ミスの背景には重大事故が潜んでいます。
配膳ミスは誤嚥に繋がるということはどういうことなのかの解説が以下の記事にあります。
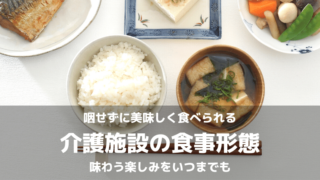
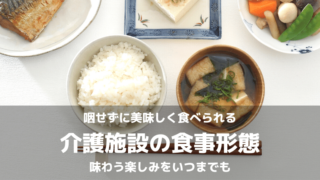
声を出してお呼びする利点
「○○様、お待たせしました」と声を出して配膳することで、配膳ミスに気付きやすいです。
認知症があっても自身の名前が分からない方は少ないです。
本人様が違うと説明できない場合もありますが、同テーブルの他の利用者様が指摘してくださることもあります。
※利用者様に頼るということではなく、職員が確実な配膳を行うことが基本です。声を出して配膳することで、無言で配膳するより配膳ミスが減らせます。
食事介助/配膳が終わったら献立の説明をしよう


配膳が済んだら介助に入ります。ご利用者様の名前をお呼びして、献立の内容を説明します。献立の中にはソテーやジュレ、ポタージュなど、高齢者様には聞き取りづらく理解できないこともあります。
これから利用者様が口にする食事の内容になりますので、解りやすく「ソテー⇒炒め物」「ジュレ⇒ゼリー/とろっとした」「ポタージュ⇒スープ/汁物」等、高齢者様が理解できる言葉に変えて説明しても良いですね。
食事介助時、利用者様が咽せ込んでしまう理由
咽せる原因はたくさんありますが、職員の介助の方法による咽せ込みは避けたいですね。
一度咽せると涙を流しながら咳き込まれる方も多いです。繰り返し咽せてしまうと食事は辛く苦しいものと認識し食思低下に繋がることもあります。
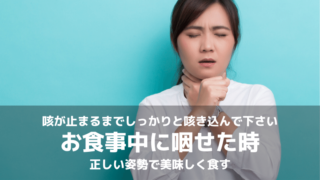
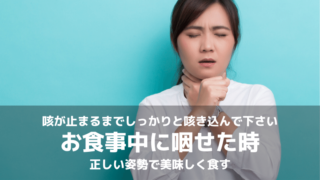
【対応方法】食事時の確認で、減らせる苦しい咽せ込み
私自身も時間に追われている際は、早く食事を済ませようと一口量を多くしたり、不十分な咀嚼のまま嚥下しようとし、詰まってしまったり、激しい咽せ込みを経験したことがあります。
咽せ込みの原因は、利用者様自身の嚥下機能の低下が理由であることもありますが、職員の不適切な食事介助で起きることもあります。
- 利用者様の覚醒状態を確認する
- 利用者様の姿勢を確認する
- 食事中の無闇な声掛けを避ける
食事介助前に、利用者様の覚醒状態を観察しよう
うとうとされている利用者様に食事介助はできません。介助前にお声掛けを行って、きちんと覚醒されていることを確認しましょう。


食事前に傾眠(うとうとしていて眠ってしまう手前の状態)されてしまう理由のひとつに早過ぎる離床があります。
特に施設は離床介助が必要なご利用者様が多い為、食事の1時間程度前から離床をかけることもあり、配膳までの時間をフロアで過ごすことになります。
座位保持が可能な時間とご利用者様の状態を考慮して、離床の順番を決めましょう。体調によっては食直前の離床が望ましい場合もあります。
利用者様の姿勢を観察する
「利用者様の姿勢を観察する」を含めて、以下の記事に介護施設でお食事前にやるべきこと5つを紹介していますので宜しければご一読ください。


『車椅子を使用して食堂まで誘導した後、椅子に座り直しましょう』と一度は聞いたことがあると思いますが、先日、新人介護職員に理由を聞かれました。
Q『車椅子には除圧クッションも使用しています。なぜ、わざわざ椅子に座り直す必要があるんですか?』
A 基本的に車椅子から椅子に座り直していただくが答えです。
車椅子から椅子に座り直していただく理由について
歩行時、ふらつきがある方は、杖やシルバーカー、歩行器、車椅子等、その方に最適な福祉用具を使用してお部屋からお食事席まで移動されています。
車椅子は椅子としての機能より移動するために作られた用具です。車椅子に長く座られていると、体重が突出した骨(尾骨、仙骨等)に圧がかかり、お尻が痛くなったり、肌が弱い方は直ぐに赤くなってしまいます。
また、椅子の高さとテーブルの高さが合っていないと、利用者様にとっては食事が摂りづらくなります。
利用者様の食事の様子を観察して、テーブルと車椅子の高さが適切かチェックしましょう。
特別養護老人ホーム等、要介護度が高いご利用者様の殆どが車椅子を使用されています。全員を車椅子から椅子に座り直していただくことが難しい施設もあるのではないでしょうか。
テーブルと車椅子の高さが適切、且つ、以下を考慮することに加えて、車椅子のフットサポートを上げ、足底(足の裏)が床に確り着いた状態であれば車椅子でお食事もやむを得ないと考えます。
- 車椅子専用の除圧クッションを使用する
- 車椅子座面が緩んでいないか確認(座位崩れの原因)
- 比較的、座位が不安定、認知症を患う方
車椅子を使用してホールのお食事席までご案内後は、椅子に座り直しましょう。
食後は再び車椅子に移乗してお部屋までご案内することになりますが、食事中の車椅子の保管場所の確保が難しい場合等、やむを得ず車椅子のままお食事となりますが、車椅子専用クッションを使用して除圧、座位崩れ予防を行いましょう。
利用者様の食事形態を確認する
現在召し上がっている食事形態が、本人様にとって適切かどうかの評価をしましょう。
以下は、ミールラウンドを含むお食事の形態についてを纏めた記事です。
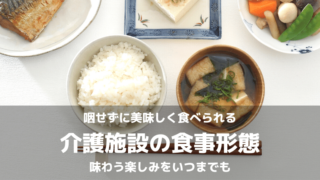
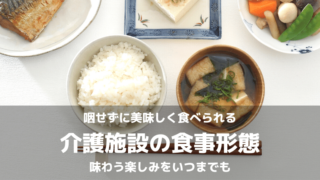
高齢者が食事中に声掛けしてはいけない理由
口腔内に食事が入ると咀嚼(そしゃく・噛み砕く)し、自身で飲み込むタイミングを図ります。高齢者の喉元を観察して嚥下(えんげ・飲み込む)するのを確認しましょう。
また、口腔内に食事が入った状態で無闇な声掛けは控えましょう。
口腔内の食事を一生懸命咀嚼(そしゃく・噛み砕く)されている利用者様に、「○さん!美味しいですか?」と声を掛ける職員がいますが、食事中は基本的に静かに見守りましょう。
何故、食事中に声掛けを控えなければならないのかについてですが、口腔内に食事が入っている状態で「美味しいです」等、利用者様に話をさせることは咽せ込みから、誤嚥(ごえん・飲み込んだお食事が食道ではなく、誤って気管に入ってしまう)の原因になり大変危険だからが答えです。
こちらも食事の形態や義歯が本人様に合っていない可能性があります。お肉やお魚だけ刻み食で提供できることもあります。看護師や管理栄養士、ケアマネジャーに相談してくださいね。
主食と副食を混ぜ合わる行為は好ましくありません。混ぜ合わせる動作でカチャカチャと音を立てることも下品です。
食事介助時、眠いから食べたくないは正答です
食事中にトイレに行きたい人もいるんです。
じゃあ、どうしたら良いですか?!😭
食事のお声掛けをした際は覚醒良好であっても、配膳時や食事中にうとうとされる方も多いです。私も眠い時に食事はしないので「眠いから食べたくない」お気持ちも理解できます。


【対応方法】利用者様には利用者様の生活習慣がある
りょうこさんがが言う「昼食は皆さん12時に召し上がって頂いています」は間違えではありませんが、どなた様にも、これまでの生活習慣があります。
私も休日は他の日より遅く起きます。また、朝食を食べ損なってしまうこともあります。
施設生活となったことで、これまでの食事の時間が、施設で決められた時間に変わってしまいます。
私たちでも、環境が変わると馴染むまでに時間が掛かりますが、慣れ親しんだ我が家を離れ、施設に入所される高齢者様にとってはなおさらですね。


100名近いご利用者様全てのご意向に添えることが難しく、朝食は8時、昼食は12時等、施設それぞれの決まった時間でのお食事となります。
「昼食は皆さん12時に召し上がっていただいています」は間違えではありませんが、お客様のお気持ちをくみ取って下さいね。
食事介助中は基本的に席を立たない
職員が食事介助中に席を立つということは、介助が必要なご利用者様の食事がそこでストップするということです。何も言わずに席を立っていませんか?
【対応方法】食事介助中、席を立たなくても良いようにするには
もちろん、りょうこさんが言うように、やむを得ず食事介助中に、中座することはゼロには出来ません。
しかしながら、席を立たなくても、食事介助に集中出来るようにするために行う段取りはあります。
お食事前に、お手洗いを済ませておくだけでも中座の頻度は下がります。
普段、私達は1時間掛けて食事をすることはありません。利用者様も同様に1時間も椅子に座っていることも厳しい方が多いです。
食事介助は30分程度が限度です。15分~30分、ご利用者様のお食事介助に集中できるように、お食事前に排泄は済ませておきましょう。
利用者様が食事中の声掛けには注意が必要な理由
食事をご利用者様に見ていただくことが大切だと言われたことが記憶に残っています。
どういうことかと申しますと…。以下に書きます。内容を想像しながら読み進めて下さいね。
職員は今、お客様の目の前で煮物の器を取り上げ、スプーンに煮物を乗せました。
スプーンに乗った煮物が、もうすぐ口元に届くまでの過程を利用者様が見ており、良いタイミングで開口され煮物が口腔内に入ります。
咀嚼中にゆっくりと再びお客様の目の前で、次の汁物の器を職員が取り上げます。
ゆっくりと汁物が目の前に来る風景を利用者様に見ていただきますが、この時にご利用者様が行うこととして、口元に汁椀(またはスプーンに救った汁物)が届くまでに
- 今、咀嚼(噛み砕く)している煮物を飲み込む
- 汁物を召し上がるタイミング、準備をされます。
この一連の流れが大切でゆっくりすぎても、早すぎても良くありません。
利用者様の表情、お口を開ける様子、飲み込む様子を観察しながら介助を行いましょう。
利用者様が、これから食す食事が口腔まで届くまでの動作を見ていただくことが大切です。
- 現在咀嚼(そしゃく・噛み砕く)している煮物を飲み込む作業
- 一息して汁物を受ける体制を自身の中で整えている状態
上記ふたつの労作の邪魔になる環境は以下になります。
- 不用意な職員の声掛け
- 音量が大きいテレビ等の音
- 行き来の多い人の動き等の周辺の環境
職員は静かに見守りながら介助をすることが大切です。食事中に「美味しいですか」等の声掛けや、「あーん」等と開口を促す行為はNGです。
繰り返しますが、優しいご利用者様なら職員の声掛けに返事をしようとされます。口腔内に食事が入った状態で息を吸うことは誤嚥(ごえん・飲み込んだ食事が食道ではなく誤って気管に入る)となるリスクが高くなります。
もちろん、声掛けは大切なことではありますが、食事中の声掛けについてはタイミングを計りましょう。
この記事を書き終えて まとめ
- 一口量が多すぎて飲み込めません。少しずつ食べさせてください。
- まだ食事が口腔内に残っています。次々と突っ込まないでください。
- 何を食べているのか解りません。私の食事はどこにありますか。
- 咽せて苦しいので、もう食べたくありません。
- お肉が硬くて噛み切れません。食べやすい大きさにしてください。
- ごはんにおかずを混ぜてしまって、不味そうだから食べたくありません。
- 眠くて仕方がないので、今は食べたくありません。
- 食事中に黙って席を立たないでください。私は何分ここで待てば良いですか。
- 一口の量を小スプーン1杯程度で、ひとくち量を崩さず一定にしよう。
- 咀嚼、嚥下の様子を観察して、飲み込みの確認をしながら介助しましょう。
- お名前をお呼びして、メニューをお伝えし、本人の目の前に配膳しよう。
- 義歯は本人に合っていますか。トロミ剤の使用も検討しましょう。
- 食事形態が適切かを検討しましょう。(ミールラウンド)
- 基本的に主食と副食を混ぜない。カチャカチャ音をたてないように気を付けて。
- 延食対応とする。覚醒されていることを確認して食事介助を行いましょう。
- 食前に排泄を済ませる。やむなく席を外す際は、利用者様に説明をしましょう。
日常の生活の中で、【食事】が楽しみのひとつである利用者様も多いです。
私がやっていたことなのですが、自分で食事をする際に、口腔内に食事入ってから咀嚼(噛み砕く)、嚥下(飲み込む)までの工程を、一度、頭の中で考えながら食事をしてみてください。多くの発見があるはずです。


様々な理由があって、誰かに手伝ってもらわないと食事が摂れない利用者様の手となって、タイミング良く食事の介助ができると良いですね。
最後まで、お読みいただきまして誠にありがとうございました。