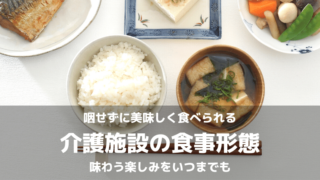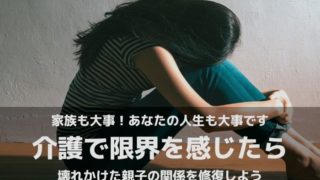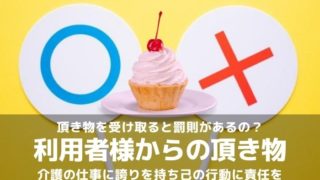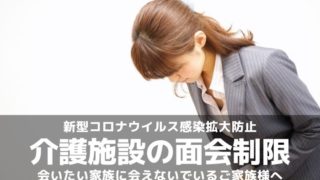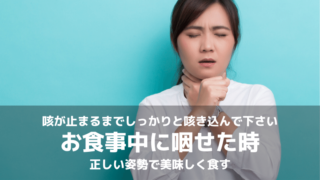ご利用者様からの頂き物は受け取って良いのか
日々、介護業務に携わる中で、ご利用者様から個別でいただき物をしたことはありませんか?その場合、どのようにお返事をして、どのように対応していますか?
お中元やお歳暮など、定期的に施設に送られてきたり、利用者様や、そのご家族から心付けとして直接、職員に金品を渡された場合、どのような対応が望ましいのでしょうか。
先日、介護職員から「良くないとは思うけど、実際、何故いただいてはいけないのか解らない」と話しがありました。
- ジュースやお菓子も受け取ってはいけないのか
- 利用者様はどのような気持ちで職員に金品を渡そうとされるのか
- いただき物をお断りする際、利用者様への伝え方
- 断り切れず受け取ってしまった場合、どのような対応が必要なのか
- ヘルパーや介護職員が気持ちよく仕事ができる環境を整えるには
- 利用者様からのいただき物を受け取ると罰則があるのか
など、利用者様から金品を渡された場合、職員としてどのような対応をするべきなのかを記事にします。
|
軽くて使いやすい看護・介護の必需品! |
お気持ちだけってお断りしたんですけど、私の伝え方が悪かったのかな。あの日以降、お声掛けをしても素っ気なくされています😢
利用者様との関係を壊すことなく上手にお断りする方法はありますか?
今回はその辺についても解りやすく記事にしますので、りょうこさんも参考にして下さいね。
利用者様から金品を受け取ってはいけない理由
利用者様から個別で食べ物や現金を頂いて良いのか、良くないのかについて「頂いてはいけません」が答えです。
良くないことはなんとなく理解できている方も多いと思いますが、何故、受け取ってはいけないのかが解らないから、受け取ったという職員もいます。

施設での対応をメインにしていますが、介護事業所でも訪問先で同じように利用者様からお茶やお菓子、金品を差し出されることが大いにあります。
今回は、頂き物をしてはいけない理由について、今ひとつ解らないという方に向けて記事に纏めていますので参考にしていただけ。
贈り物を受け取る施設と全てお断りしている施設がある
介護老人保健施設、介護福祉施設、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所で働く知り合いのケアマネジャーに、各勤務先では、どのような規定になっているかを聞いてみました。
質問した全ての施設で、介護職員は個人的に、利用者様やご家族からの頂き物は禁止となっていました。
一方、ご家族様からお中元やお歳暮等を施設宛てに差し出された場合、受け取る施設もあれば、丁重にお断りしている施設がありました。
つまり、個人的に利用者様やご家族からの金品の授受に関しては禁止していますが、施設宛てであれば、受け取る施設があったということになります。


重要事項説明書や就業規則・倫理を確認してみましょう
介護サービス利用時に説明させていただく、重要事項説明書の中にある禁止事項として「利用者又は家族からの飲食、物品、金銭の授受」のような文言があると思います。
ご入居時に、金品の授受についてを含め、説明をさせていただき、同意を得て署名、捺印をいただいています。

※重要事項説明書ではなく、ご入居に関する注意事項として記されている場合あり。
また、施設で働く職員や訪問介護事業所で働くヘルパーの場合、就業規定や倫理規定に金品の授受についての記載があると思います。一度、職場で確認してみて下さいね。
ご利用者様(ご家族様)は、施設と契約を締結しています
利用者様はご入居時に、施設契約を締結しています。同様に職員も労働条件の説明を受け、同意し施設と契約して現在の職場でお仕事をされています。

どういうことかと申しますと、利用者様は施設のお客様であり、そこで働く職員にとっても、利用者様はお客様ということです。
無料でサービスを提供しているわけではなく、施設や事業所の職員、ヘルパーとして介護計画に沿った介護サービスを提供し、報酬を頂いています。
関わりを持つことで、親しくなった場合であっても、職員個人の知り合いでも友人でもなく、お客様であるということです。
例えば、介護職員ひとりがお菓子や飲みもの、現金を含めて頂いてしまった場合を考えてみましょう。
他の職員が丁重にお断りすると「A職員は気持ちよく受け取ってくれたのに、冷たい人」と、断った介護職員がご利用者様からみると、冷たい人となってしまいます。
ひとりの利用者様に、複数の介護職員が対応することは、施設、在宅に限らずあると思いますが、関わる職員の対応は統一することが大切です。
関わる職員の対応を統一するということは、施設や介護事業所が先頭に立って、職員が働きやすい環境を整えるべく、きちんとした説明(教育)をするということです。
ご利用者様は既に必要なサービス利用料を支払っている
訪問介護やデイサービス他、介護保険を利用して受けているサービスには、利用料が発生しています。
サービスをご提供時、利用者様と職員の目線は同じであるべきであり、受け持つ利用者様への対応も平等であるべきです。


ご利用者様が職員に食べ物や金銭を差し出す理由
訪問介護事業所のヘルパーや、施設介護職員が利用者様に関わることで「いつもありがとう」と、お菓子や飲み物等を差し出されることがあります。
私達施設職員は、ケアマネジャーが作成するケアプランという、介護計画書に沿ってサービスを提供させていただいているので介護をすることは当然であり、それが仕事です。
仕事と言うことは、介護サービスを提供することで、報酬を得ているということです。
では、なぜ利用者様やご家族は職員に金品を差し出されるのでしょうか。
介護をさせて申し訳ないとお駄賃の気持ちがある
介護をすることが仕事であっても、お風呂や排泄の介助を受けている利用者様にとっては、感謝の気持ちを伝える方法として金品を差し出されることがあります。
特に見返りを求めていない気持ちが大きいのですが、一度受け取ったらそれで終わりではありません。
一度受け取ってしまうと、繰り返されるということです。
訪問する度に、お茶やお菓子、時には現金を包まれることもあります。
何度も何度も断り切れず、一回だけと受けてしまったことが切っ掛けで、再び差し出されます。
利用者様にしてみると「この前は、受け取ってくれたじゃない」と、結局は複数回、利用者様から金品の授受をすることになります。
頂き物を個人的に受け取ってはいけないことは理解しているゆえ、歯止めが掛からず気が重くなり「どうしよう」と悩む職員が実は少なくありません。

独居で寂しい。介護職員対利用者以上の関係を持ちたい
自宅に訪問してくれて、買い物やお掃除、入浴や排泄の支援など、身内がやるようなことを自分の子供や孫ほどの年齢のヘルパーさんがやってくれる。
優しく関わってくれる。
介護職員と利用者の関係を超え、いつもそばにいてほしいと言う気持ちが芽生えます。
利用者様に寄り添うことは介護を行う上で、大切なことです。
とはいえ、利用者様は家族や友人ではなく、お客様であることを前提に関わることが大切です。
利用者様に立ち入る線引きについて、ひとつの目安としてお伝えするならば、担当する利用者様全員に対応できることまでとします。
例えば、寂しい時に、電話で相手をしてほしい利用者様がいたとします。

お一人ならば対応できても、自分の担当する利用者様全員が寂しい時に電話で相手ができるのかということです。
就業規定や倫理規定では、利用者様に個人の電話番号や住所等、個人の情報をお伝えしてはいけませんとなっているはずです。親しくなっても、担当する利用者様はお客様だということを忘れないで下さいね。
他のご利用者様以上に、自分を特別にみてほしい
施設でよく見られます。何かを行う際は一番先に対応してほしいご利用者様。食事も一番に配膳してほしい。お薬も一番に飲ませてほしい。横になる時も一番先に寝かせてほしい。
ご家族様もまた根底には、親を特別に見てほしいという思いから、金品を提供されることがあります。
ご利用者様との距離は近過ぎず、遠過ぎずを保つこと
施設介護職員は、早番、日勤、遅番、夜勤等シフト制の勤務をしています。
当然ですが夜勤業務は、利用者様が就寝前から目覚める朝まで同じ職員が関わることで、関係上、施設職員と利用者様であることは理解できていても、家族のような関係になっていきます。

馴染みの職員がいることで、利用者様は安心して生活できます。
近過ぎず、遠過ぎずの関係は難しいですが、ご利用者様に、広い視野を持ち、気を配る、目を配る、心を配ることが大切です。
ご利用者様との距離を適切に保つことが良い関係を続ける秘訣
言葉遣いはどれだけ親しくなっても、敬語を使うことをおすすめします。
ご入居されて3ヶ月も経過すると、職員の顔や名前を覚えてくださる方もいらっしゃいます。
毎日コミュニケーションを図ることで利用者様との距離が縮まりますが、親しみを持って関わることと、崩れた言葉で慣れ慣れしいのとは違います。
お客様と職員という関係であるということを忘れないで、節度をわきまえて関わりましょう。
ご利用者様との対話時、留意すべき点
特に女性の利用者様は、お話しが大好きな方が多いです。
利用者様と関わることで、親しくなると、つい、利用者様は施設のお客様であることを忘れてしまい、職員個人のプライベートなことまで話し過ぎてしまうことがあるので注意が必要です。
職員が自身のプライベートなことまで話し過ぎると、利用者様に余計な気を遣わせてしまうことになります。
そんなつもりはなくても、餞別やお礼等の礼儀を気にされるご利用者様は多いです。
- 職員や子供が妊娠した
- 子供が受験し合格した
- 子供が結婚した
- 夫と別れた
- 孫が生まれた
- ○月に仕事を辞める
- お金がない

利用者様が上記の内容の話を聞くことでお餞別やお祝いを気にされます。
上記内容は利用者様から直接うかがったお話しの一部です。利用者様に話したつもりでも、実は施設長が知っていたりすることも割りと多くあります。
利用者様とは、誰に言われても恥ずかしくない内容のお話しをしましょう。
また、相手はお客様であることを忘れないことと、話すだけではなく、利用者様のお話を聞くことも大切です。
|
履きやすく長く履ける人気のシューズ |
金品授受は不要とお伝えすると返ってくるお返事
利用者様や、そのご家族からお菓子や飲み物等を出された時に、職員が何度お断りしても下げてくださらず、出した物を受け取らない職員に対して、不快感を抱くことがあります。
職員に物を受け取らないよう指導している施設として、利用者様やそのご家族に直接お話しさせていただくことがあります。
以下は特に多い利用者様やご家族からのお話です。断り切れずに受け取ったお菓子やジュースなのですが、利用者様からは意外なお返事があります。
対価をを求める利用者様
「あれだけやってあげたのに、対応が遅い」と不満を持たれる。
その時は、そのような気持ちはなくても、自分を優先してほしいという気持ちが根底にあり、それが叶わないと不満となってしまいます。
職員が悪いといわれる
「冷蔵庫に頭を突っ込んで、あさって行った」と仰る利用者様もいらっしゃいました。
認知症が軽度ある方でしたが、「いつの間にか職員に持って行かれた」と話されることもありました。
施設に対する不信感
「毎週お菓子を5~6袋買ってくるように言われるのですが、母一人でこんなに必要ですか?」と。
職員が物を受け取ることで、次に会った時の分をと、本人様のみならず、ご家族様にもご負担を掛けてしまいます。
利用者様と長く良好な関係を築くために頂き物をしないというのが定義です。
物を頂くことで言わなければいけないことが言えなくなる
本来なら、注意しなければいけないことが起きても、普段からお菓子などをいただいていることから、注意がしづらくなってしまいます。
ご利用者様と職員と良い関係を築くために、例え今回だけでも、1回だけでも、物を受け取らない方が、のちのちの業務がスムーズに行えます。
ご利用者様同士で物品のやりとりは禁止となっている
水分やお食事に制限があるご利用者様も、施設には多くいらっしゃいます。
利用者様同士の食べ物や飲み物のやりとりが禁止になっていると思いますが、ご利用者様に禁止していることを、職員が行うのはおかしいですね。

※私が働いている施設では、一日の摂取カロリーや塩分、糖質や水分量等、医師の指示で制限がある利用者様も多く、更には、認知症を患う方も多いという観点から、利用者様同士の金品のやりとりを禁止としています。
ご利用者様から金品を差し出された際の断り方
例えば大切に思っている方にプレゼントをした時に「受け取れません」と断られたらどのような気持ちになるでしょうか。
ご利用者様のお気持ちを無下にお断りするのではなく、感謝の気持ちを伝えて、受け取れない理由をお話しましょう。

「職場の規則で、お客様から物を頂くと働けなくなってしまいます。○様とは今後もお付き合いさせていただきたいのでお気持ちだけいただきます。ありがとうございます。」
「ご利用者様から物を頂いたことでトラブルになり退職した職員がいます。お気持ちは大変嬉しいです。ありがとうございます。」
最初にお菓子などを出された際に、お断りすることが肝心です。
「素直じゃない」等もしかしたら利用者様からなじられるかも知れません。
ですが、頂き物をしなくても、振る舞いや丁寧な仕事(介護)で、利用者様との信頼関係は築けます。
また、例え受け取らないことで、他に不満を漏らしても、気にすることはありません。
逆に「A職員は受け取ってくれたのに」と言われる方が困るのではないでしょうか。
一度頂いてしまうと二度目に断ることができなくなってしまいます。頂き物をしなくても、ご利用者様と良好な関係は作れます。
どうしても断り切れずに受け取ってしまった場合の対応
「誰にも言わなきゃ解らないから」「ひとりでは食べきれないから」「汚くないです」「お茶も付き合えない人に介護してほしくない」等、利用者様によっては、出した物は下げられない頑固な方もいらっしゃいます。
お断りしても、しつこく勧められる場合は、一旦受け取り、職場に持ち帰り、必ず上司に報告しましょう。
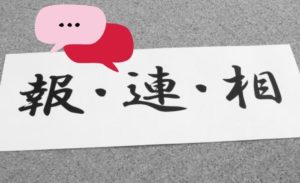
度重なるようであれば、事業所、施設で対応していただきましょう。
職員が気持ちよくお仕事をする為に大切なこと
利用者様と直接関わる介護職員が、良好な関係を築くために、施設や事業所が利用者様(ご家族)と契約を締結する際、注意していただきたいこととして、施設(事業所)では利用者様やご家族からの、菓子やジュースを含む金品の授受を一切ご遠慮させていただいている旨の説明をしましょう。
お茶などの一切の厚意をお断りするのか、お茶やお菓子等は可とするのかを同じように雇用契約を交わし入職時に行うオリエンテーション等で、職員への説明が必要です。
職員に施設の方針、線引きを示すことで、現場で直接ご利用者様と関わる職員は、悩みを持つことなく、気持ちよくお仕事ができます。
ひとりの職員が差し入れを頂いてしまうことで、次に訪問したヘルパーに迷惑が掛かることも最初に説明するとよいですね。
頂き物に関しては、施設、事業所それぞれの専門職が連携して、統一した対応を行うことが大切です。

ご利用者様から金品を受け取っても処罰はない
[省令]指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
上記のように、居宅介護支援指定基準(運営基準)には、ご利用者様に必要なサービスを選択していただけるよう事業者等から金品を頂いてはいけませんとあります。
利用者からの金品授受はトラブルの元
一方、施設にご入居中のご利用者様やご家族様から介護職員に金品を渡そうとされ、例えそれを受け取ったとしても法的な罰則はありません。
基準省令などにおいても、ご利用者様やご家族様からの頂き物について、明文化されているものはありません。
お茶やお菓子、お心付けを受け取っても処罰はありませんが、高齢者や認知症を患う方から受け取る金品によっては、勿論、詐欺事件として本人やご家族から訴えられた事例があります。
認知症を患う方は、あげたことを忘れてしまい、盗られたという事があります。「あげると言った」「言ってない」のトラブルとならないように、受け取らないことをおすすめします。
|
不可解な行動の裏にある心理が解る一冊 |
この記事のまとめ
今回は、「介護」というお仕事をする中で、ご利用者様から、又はご家族様から飲料、菓子、金銭などを差し出された場合、どのように対応したら良いかについて書いてきました。
また、ご利用者様から金品を受け取ってはいけない理由や、ご利用者様は、どのような気持ちから職員に対してお茶やお菓子、金品を差し出されるのかについても触れました。
物を作るお仕事、物を売るお仕事他、お仕事には沢山の職種がありますが、「人に関わり、寄り添う職業である介護」もまた、お仕事です。
どうしても、直接、ご利用者様の生活に関わることから他のお仕事に比べると、感謝されたり、お礼をされたりに、繋がりやすいのだと思います。
今回の記事の振り返り
- 利用者様は施設や事業所のお客様です。関わることで親しくなっても、家族や友人ではなく、そこで働く職員にとってもお客様です。
- 介護サービスを提供し、既に報酬を頂いている為、ご利用者様からそれ以外の報酬を個別で受け取ってはいけません。
- 個別で物を受け取ってしまうと、その利用者様に言わなければいけないことが言い辛くなってしまう。平等な介護が難しくなってしまう。
- ご利用者様との距離は近過ぎず、遠過ぎずを保つことが大切。親しみを持ち関わることと乱れた言葉で馴れ合いになることは違います。
- 利用者様が金品を差し出すお気持ちを理解し、無下にしない。理由をお伝えし、お気持ちに感謝する。
- 職員が気持ちよく仕事をする為に、施設や事業所は方針や線引きをご利用者様、職員に示すこと。曖昧にしないことが大切です。
- 利用者様から金品を受け取っても処罰はありませんが、介護職員としての仕事に誇りを持ち、責任ある行動をとりましょう。
ひとりの介護職員としてのプライドを持つ
就業規則には、頂き物をしてはいけないとされていますが、法的に処罰の対象にはならないからと言っても、訪問介護の場合は、お仕事をするために、ご利用者様のご自宅に訪問して介護を行っています。
サービスの内容によっては、一人の職員が、利用者様のご自宅の浴室やトイレに入ったり、電子レンジ、冷蔵庫等に触れ、キッチンにも立ちます。
事業所でNGとされている倫理違反をしてしまい事業所に秘密を作ってしまうと、「お金がなくなった」等のトラブルが発生した際、胸を張って潔白を証明しづらい状況に陥ります。
介護の仕事に誇りを持ち、己の行動に責任を!介護のプロとして培った介護知識、介護技術を持ち、誠実に関わることで、ご利用者様やご家族様と良好な関係を作ることはできます。

以上でございます。最後まで読んで下さって誠にありがとうございました。








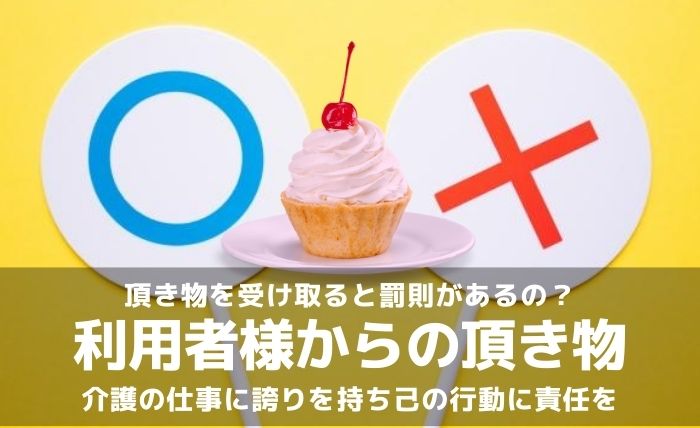
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32ba4de8.719839bb.32ba4de9.2fe734c4/?me_id=1344660&item_id=10001289&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Finfirmiere%2Fcabinet%2F8094%2Fgn01310738-m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32ba74e0.b50afeaf.32ba74e1.e535a9f4/?me_id=1333268&item_id=10000026&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Flittlemagic%2Fcabinet%2Fitem%2Fnas%2F3-2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32bae58b.6f0e6400.32bae58c.cb0590fa/?me_id=1227000&item_id=10001141&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuperfoot%2Fcabinet%2F09551927%2Fimgrc0114816081.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d8ed884.ba07fa0f.1d8ed885.2e673655/?me_id=1213310&item_id=20285643&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3638%2F9784866513638.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)