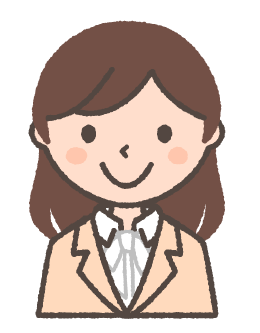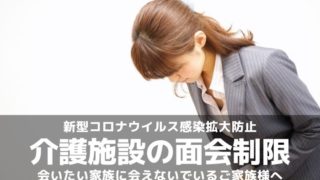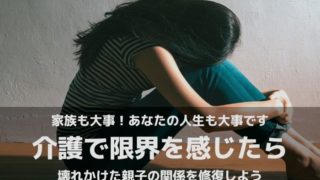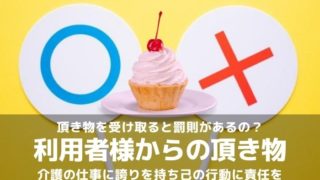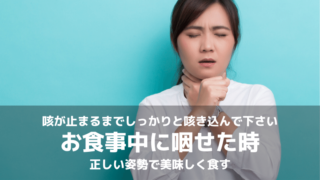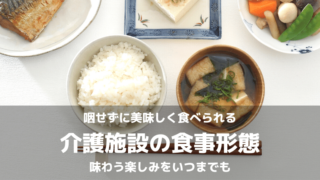入浴を拒否される認知症ご利用者様の理由
お風呂が大好きなご利用者様は多いのですが、お風呂が嫌いなご利用者様もいらっしゃいます。
お風呂に拒否があるご利用者様は、どこの施設にもいらっしゃると思いますが、今回は入浴拒否があるご利用者様の理由と対策についてを記事にします。
介護施設で働く職員様、自宅で介護をされているご家族様他、介護に興味をお持ちの方に、少しでもお役に立てれば幸いです。
こんにちは。めぐろの介護新聞にお越し頂き、誠にありがとうございます。
前回は、ご入居頂いているご利用者様に、心地良くお風呂に入っていただく為には、入浴前の準備が必要ですといった内容の記事を公開させていただきました。
- ご利用者様が入浴を拒否する理由について
- 入浴を拒否をされるご利用者様の対応方法
- 入浴拒否をされるご利用者様に行ってはいけない対応
- 基準省令にある週2回の入浴が困難な場合の対策
など、介護施設で起こるご利用者様が入浴を拒否する理由と対策についてを記事にします
認知症を患う方には入浴の意味が理解出来ない方もいる
一般的に「お風呂」と聞けば、脱衣し浴室に入り、顔を洗い、髪を洗い、身体を洗い、浴槽に浸かり温まる等、一連の動作が記憶にあります。
一般的に「お風呂」と聞けば、一日の疲れを洗い流し、リフレッシュすると連想でき、実際に浴槽に浸かるイメージが脳裏に浮かびます。
一方、認知症を患う方の中には、「お風呂」の記憶や思い浮かぶイメージがありません。何のために衣類を脱ぐのか解らない為、恐怖心を覚えたり、不安を感じたりするのです。
どちらの施設でも入浴を拒否されるご利用者様はいらっしゃると思いますが、何故、お風呂に入りたくないのかの理由を探り、その理由をひとつずつ解決していくことが大切になります。
- 知らない場所に連れて行かれる
- 洋服を脱がされる
- 生温かい浴室の違和
- 身体が濡れる 顔が濡れる
- シャワーのお湯を掛けられる
- お湯の中に身体を沈められる
認知症を患う方の中には、環境の変化や不安、恐怖、羞恥、違和を感じると拒否に繋がります。普段行う介護以上に優しいお声掛け、対応が求められます。
認知症を患う方の環境の変化は、混乱を増大させます。毎日過ごしているフロアから、職員に促されるまま施設によっては、エレベーターに乗り浴室という知らない場所に連れて行かれる不安は大きいです。
環境の変化とは、見慣れた風景、聞こえる音、感じている雰囲気が変わることです。住み慣れた自宅を離れて施設にご入居されることも、同じように環境の変化です。
靴を脱ぎ、裸足に感じる普段と違う床材ひとつにおいても不安感を抱きます。
施設に新規入居される認知症を患うご利用者様が、施設での生活に馴染まれる期間として、概ね3ヶ月~半年程度掛かります。
認知症を患う高齢者様にとっての環境の変化に対する身体的、精神的不安は、私達が、枕(環境)が変わって眠れないこと等、比ではない大きな不安、恐怖を抱いていることを認識しましょう。
高齢者様の環境が変わるということ
施設に入居される方の多くは、ご自宅で生活をされており、何かしらの疾患や、自宅で転倒、骨折されてしまい入院となり、退院後、ご自宅での生活が困難な状況から、施設に入所となるケースがあります。
どういうことかと申しますと、自宅⇒病院⇒施設と数ヶ月で環境が転々と変わってのご入居となるということです。
介護が必要な身体になり、帰りたい自分の家に帰れないご利用者様のお気持ち。
涙されるお父様、お母様も多いです。ご本人様はもとより、ご家族様も、私も「自宅が一番」だということは解っています。
人にはそれぞれの人生があります。私達施設職員に出来ることは、ご利用者様のお気持ちを受容し共感することです。
様々な理由があって、親を、施設にあずけるご家族様の思いをくみ取り、ご利用者様とそのご家族様に、寄り添う気持ちを持って誠実に対応しましょう。
介護を学ぶ上で、最初に学ぶ受容と供給
受容とは、ご利用者様のありのままの姿を、否定も肯定もせず、無条件で受け入れること。
共感とは、ご利用者様のお気持ちを理解し、あたたかく寄り添うことです。
入浴を嫌う利用者様に入浴は気持ち良いものと認識して頂くために
先ずは拒否の理由は何かを探すことが大切ですね 。
認知症を患う方の入浴拒否を解決するヒント
入浴のお声掛けを行った際、表情が険しい、口調が強い時は、いわゆる「入浴」に対して不穏な状況です。
例え、お声掛けを続けても、良い結果には至らないので、一旦は、入浴のお声掛けは終了しましょう。
引き続き、以下に、私が介護職員として働いていた頃に経験した、入浴を拒否するご利用者様の理由と解決に向けた対応方法をお伝えします。
お風呂に入るということを理解して頂きましょう
「はなこさん!はなこさんのお風呂の順番です。どうぞ。」
と、介護職員が入浴のお声掛けを行っても、伝わっていないことがあります。
「はなこさん、ちょうど良い湯加減です。一緒に一番風呂に入りませんか?」等、お声掛けの方法を変えてみると伝わることもあります。
他にも、「温泉」ですとか「銭湯」等、用いる言葉を変えることで理解できる場合があります。
また、加齢に伴い耳も遠くなっています。お風呂は理解出来ていても聞こえていないこともあります。
よく、老人性難聴を患う方に対して、大声で一気に話しかける職員がいますが、普通の声で良いです。はっきりと、解かりやすく、短く区切って話しかけてみて下さいね。
お風呂が解らないご利用者様に入浴をイメージする物品を準備する
ご入居者様がお若い頃は、銭湯を利用されていた方も多いです。
本人様のシャンプー剤や固形石鹸、タオルや軽石等を入れた湯おけや洗面器を用意しておき、入浴時はお風呂グッズをお持ちいただくことで理解される場合もあります。

また、月別カレンダーに入浴日の目印を付けることも有効です。ご利用者様と一緒に、今日の日付け、カレンダーの目印を確認し入浴日であることを理解して頂きましょう。

施設では、ご利用者様の入浴時の着替えの準備を職員が行うこともあると思いますが、ご利用者様と一緒に着替えを準備しましょう。
ゆったりと入浴していただくために環境を整えよう
決められた時間内に入浴を終えるために、職員が慌ただしく動くことで、ご利用者様が入浴に集中できなくなります。
入浴に拒否がある方をお風呂にお連れする際は、周りの環境にも配慮が必要です。
入浴のお声掛けから浴室までの誘導、脱衣から浴室での洗身、洗髪や退浴後の着衣、ホールまでのお送りを一人の職員で行うマンツーマンでの対応が望ましいです。
また、隣接する浴室がある場合は、つい立てやカーテンなどで仕切り、プライバシーの配慮に努めましょう。

利用者様がお風呂嫌いになった理由
職員のお声掛けの方法や介助の方法に問題があり、拒否をされている場合があります。拒否の理由を知ることからはじめて、入りたくない理由をひとつずつ摘み取っていきましょう。
目や耳にお湯が入らないように配慮しましょう
入浴時に洗髪を介助する際、ご利用者様の殆どは目を閉じる事になります。
裸の状態で目を閉じるという行為は、無防備となり、不安や恐怖心を抱きます。
ご利用者様に安心していただけるように、入浴に限らず、何かの介助に入る前に、これから何のために、何を行うのかのお声掛けを行い、理解して頂くことが大切です。
ご利用者様に、「髪を洗うこと」「シャンプー剤を使うこと」「泡が目に入らないように気を付けます」「安心して下さい」等の声掛けが理解して頂けると、自ら耳を塞がれたり、目を閉じられるご利用者様もいらっしゃいます。
ご利用者様へのお声掛けは、そこまで大声でなくても、はっきりと、解りやすく短く区切ってお伝えすれば聞こえる方が多いです。大声で優しいお声掛けは難しく、受け取り方次第では、叱られているように感じる方もいらっしゃいます。
また、それでも不安そうにされたり、動揺されるご利用者様にはシャンプーハットを使用したり、タオルを本人にお渡しして、目を塞いで頂きましょう。

入浴当日の入浴予定者の体調を観察しましょう
高齢になると、運動量が減退して筋肉が減少したり、食事や水分の摂取量も少ないことから便秘症を患っている方が多いです。
自然排便が困難となった場合、腸の機能を整えるお薬を内服されていたり、下剤を使用している方も少なくありません。
下剤を使用して、排便のコントロールを行っているご利用者様は、下剤に反応する排便がゆるくなり、何度もトイレに行かれる場合があります。時には間に合わず、失敗することもあります。
そのような状態の日に、一人ではなく誰かに手伝ってもらっての入浴に、気が進まない利用者様のお気持ちを理解しましょう。
また、前日あまり眠れていなかったり風邪気味との自覚症状を訴えられる等がある場合は、ご利用者様の不安を傾聴して、対応出来る入浴の内容をお伝えしてみましょう。
「そうなのですね。不安ですね。解りました。大丈夫ですよ。私が対応させて頂きます。」とお声掛けしてみてもよいですね。
ご利用者様自身が気になっているお困りごとを理解している職員が対応することで、安心して入浴に応じられる方は多いです。
通院等の外出日に、下剤の反応便が続くのは避けたいところです。外出については、予定として事務所や担当の看護、介護フロアが把握しているはずですが、念のため、前日に外出予定があることを看護師に伝えておくと安心です。
勢いの良いシャワーが嫌いな方の対応
割りと多いのが、シャワーをそのままご利用者様に向けることで、湯圧を嫌う方がいらっしゃいます。

身体に当たるシャワーの勢いを弱める方法として、ご存知の方も多いと思いますが、シャワーから出るお湯を、ご利用者様ではなく、職員の手の平で勢いを弱め、こぼれ落ちるお湯をご利用者様に掛ける方法があります。
それでもNGのご利用者様がいらっしゃいましたが、シャワー禁止として湯桶(洗面器)や手桶にお湯を溜め、洗髪時の頭部、洗体時の身体に掛けてあげることで、入浴拒否が解消された方もいらっしゃいます。

その他、施設のお風呂に入りたくない理由は様々
施設に入居される前までは、夕食後や寝る前等、その方なりの入浴に関する習慣がありました。施設に入居されたことで、ご利用者様のこれまでの生活習慣がかわってしまうことを理解しましょう。
また、A職員の入浴のお声掛けに拒否があったご利用者様でも、B職員がお声掛けをすると入られることがあります。
同性介助を希望される方、逆に同性の介助を拒否する方もいらっしゃいます。本人様の入浴に関する拘りや思いを可能な限り叶えましょう。
他にも、過去に受けた手術痕を見られたくない方、皮膚に疾患があり身体を見られたくない方、ウイッグ(人工の髪で作られたカツラ)を外したくない方など、本当に様々な理由があって入浴を拒まれます。

そんなこと…と職員は思っても、本人様にとっては真剣です。
おひとりおひとりのお悩みを拭い去り、自宅で入るような感覚で施設のお風呂をご利用いただけるようになってほしいと願っていますし、その為に、日々、誠実に対応しています。
入浴を拒否するご利用者様に絶対に行ってはいけないこと
入浴拒否が続き、長く入浴が出来ていないご利用者様に、お風呂に入っていただきたいがために、嫌だと言うご利用者様を無理やり入浴させることで、ご利用者様が抱く入浴のイメージは「恐怖」「屈辱」になります。
入浴拒否がある場合は、拒否の理由を探り、どうしたら入浴していただけるのかを介護職を含めて、専門職である担当医師、看護職、生活相談員、ケアマネジャー他、担当する職員と、ご家族様を交えてカンファレンスしましょう。
入浴拒否:ご利用者様の気持ちと職員の気持ちについて
このブログを読んで頂いている方は、介護職に興味がある方や既に介護のお仕事に就かれている方、又は在宅で介護をされている方等、介護に関わりがある方が殆どだと思います。
10年以上前になりますが、実際に経験したことを書いた方が、私の思いが伝わるのではと、思い、以下で書かせて頂くことに致しました。
私が新人介護職員として施設で働き始めて数ヶ月が過ぎた頃に経験した実例です。
2週間以上入浴拒否が続く認知症を患うK様(女性ご利用者様)
何とか今日こそ入浴をと、看護師より朝の申し送りがありました。当日のリーダー介護職から2人介助(お一人のご利用者様に2名の介護職員で介助)でK様の入浴をするように指示がありました。
清潔の観点から長く入浴出来ていないご利用者様に、やむを得ず強制的に入浴していただくということです。
一緒にK様の入浴介助を行う先輩職員から、衛生面を考慮すると仕方のないことと言われました。
午後からの入浴で一番最後に実施することになっていたので、他のご利用者様を浴室にご案内の途中、何度かK様に、もう少ししたら入浴であることをお伝えしていましたが、K様からのお返事は「ありがとうございます。家で入ってきたから今日は結構よ」と軽めの拒否。
他のご利用者様の入浴が済み、いよいよK様の入浴になりました。
K様の移動手段は車椅子でした。
先輩職員が入浴のお声掛けを行いましたが、やはり拒否がありました。「お着替えだけ」という約束をして浴室まで半ば強引に車椅子のK様を浴室へ誘導。
その間、K様は「ちょっと!どこに連れて行くのよ」「やめなさいよ」と。
浴室に到着するとK様は車椅子を自操(ご自身で車椅子を操作)して浴室から出ようとされますが、認知症があり入り口が解らず苛々されてしまいます。
「Kさん。さっと身体を洗いましょう」と声を掛け、素早く上衣を脱いでいただこうとしますが嫌がります。
先輩職員より腕を持つよう言われ、私はK様の両腕を持ち、先輩職員は嫌がるK様の衣類を素早く脱衣します。
無理矢理、着ている衣服を脱がされ「やめて」「助けて」と声を荒げるK様。
私に対しても「離しなさいよ。警察を呼びますよ!」と手を払いのけ顔を叩かれます。
裸になったK様を入浴用の椅子に2人がかりで座って頂き、浴室へ。
拒否が強い為、洗髪時、シャンプー剤が顔に流れたりして、更にK様は興奮されてしまいました。
K様は小柄できゃしゃな方でしたが、どこからこんな力が出るのかと思うほど、抵抗が止むことはありませんでした。
浴槽に浸かることはありませんでしたが洗髪、洗身はできました。
K様の介護記録に一緒に介助をした先輩職員の記録がありました。
強い入浴拒否あり、2人介助にて対応。大声、暴言、暴力行為あり。と。
朝の申し送りで今日こそ入浴をと話された看護師や、当日の介護リーダーの2人介助での入浴指示について、問い詰めたり、責めたりする為に事例を挙げた訳ではないことを先に申しておきます。
記事を書き進めていくうちに、K様のことを思い出しました。K様に気持ちよく入浴して頂くために、他にも試してみることはあったのではと。
そのような介助に、私自身も関わっています。申し訳ない気持ちが10年以上経過した今でも心に残っています。
この記事を読んで頂いている読者様に想像して頂きたいのですが、「イヤ」だと発している方を、無理やり、力ずくで、二人がかりでお風呂に入れられた場合、どのような気持ちになるでしょう。
介助した職員にとっては、大声、暴言、暴力行為となりますが、K様のお気持ちはどこへいってしまったのでしょうか。
無理やり着ている衣服を脱がされ、恐怖のあまり、「やめて」「助けて」と声を荒げたり、両腕を掴まれた職員の手を振り払ったり、叩いたりすることは当然ではないでしょうか。
無理矢理の入浴となったK様にとって入浴は、精神面の安定やリフレッシュどころか屈辱として心に深い傷を負うことになります。

信頼関係は崩れ、入浴だけではなく、お食事や服薬介助などすべての介護を受け入れなくなってしまうこともあります。
拒否をされるご利用者様に対しても、人として尊厳を尊重した介護は基本です。
入浴拒否があり基準省令である週に2回の入浴が出来ない場合
一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、病院等、一週間に2回の入浴、もしくは清拭を行うことは指定基準省令として確かにあります。
週に2回の入浴が困難な利用者様に行った対応を記録に残しましょう
看護、介護記録に入浴の可否を残すと思いますが、「入浴した」「入浴していない」には「入浴していない」に当たりますのでそのままを記録します。
次に、入浴には至らなかった経緯を、やはりそのまま記録します。
介護記録
利用者名:目黒 結紀菜様 14:40
入浴のお声掛けに強い拒否あり、時間をおき、介護士から看護師に対応を変え、入浴にお誘いするも興奮状態となり、浴室にご案内することも困難な状況にて、居室内にて衣類交換のみ実施した。次回、○月○日に入浴日を振り替え実施予定。
介護記録
利用者名:目黒 結紀男様 10:15
入浴のお声掛けに拒否は見られたが、何とか浴室まで誘導。浴室内カーテン越しに聞こえる他ご利用者様の声に反応され、再び表情険しく脱衣困難な状況となり、足浴、衣類交換のみ実施した。翌日、〇月〇日に振り替え入浴予定。
上記、記録の内容に付け加えることとして、実際にご利用者様の発言も記録した方が次回の入浴時のお声掛けに役立ちます。

また、2つ目の記録には、拒否はあっても浴室までの誘導が出来ている為、次回の対策として静かな環境での対応を行う為、入浴時間の変更を検討しても良いですね。
担当する専門職、ご家族様を含めて対策を検討しましょう
ご利用者様が信頼する医師の言葉があれば、スムーズに入浴出来る場合があります。
必要であれば、担当する職員(医師、看護師、介護士、生活相談員、ケアマネジャー、作業療法士、理学療法士等)ご家族様を交えてカンファレンスを実施し、今後、どのように対応していくのかを検討しましょう。
カンファレンスやサービス担当者会議を実施した記録をすることで、入浴拒否があり、基準となっている1週間に2回の入浴が出来ていない理由として残ります。
どの施設でも入浴を拒否されるご利用者様はいらっしゃると思いますが、ありとあらゆる対策を行い、対応しています。
それでも、記録がない、あっても「入浴していない」のみとなると、問題となる可能性が高いです。

都道府県他、指摘があった場合、必要となるのが様々な記録、議事録等の書類になります。入浴拒否をされているご利用者様に行っていることは、細かく記録を残すことをおすすめします。
入浴拒否されるご利用者様に行った対応を共有しましょう
入浴に限らず、拒否が見られるご利用者様に行った対応と、結果、ご利用者様の反応はどうであったのかを、職員全員が共有する為には記録が必要です。
「入浴した」「入浴していない」のみの記録では、どのような経緯があって入浴出来なかったのか、次回、入浴を担当する職員は解りません。
更に、次回入浴のお声掛けを行っても、前回の拒否された時と同様の結果となる可能性が高いです。
「このような声掛けに笑顔が見られた。応じて頂けた。」「このような対応に表情が険しくなった。口調がきつくなった。」等があると、次に対応する職員は動きやすいですね。
この記事を書き終えて・まとめ
認知症を患う方が、入浴を拒否されるご利用者様には「入浴」「お風呂」の意味が理解できていないことがあります。
「お風呂」は理解できても、お風呂の入り方を忘れてしまっている方もいらっしゃることを理解して、お声掛けを多く持ち、優しく対応しましょう。
また、浴室での本人の動向を観察していると、顔を自身で洗われた後、再び顔を洗う等、同じ動作を繰り返す方もいらっしゃいます。
人それぞれ、頭から洗う、顔を先に洗う等、入浴の手順は違うものです。
介助やお声掛けが必要な時に、職員が次の動作を促すことで、気持ちよく入浴できることもあります。
良く私が実践していたことなのですが、自分が入浴する際、どのように身体を洗うと気持ち良いのかを考えながら入浴してみるのも良いです。
部位によっては優しく洗わないと痛みを感じたり、髪を洗う際も、気持ち良く感じて頂ける洗髪の方法や、身体を拭く時も、拭き忘れがちな部位の発見、痛くない身体の拭き方等、自分の身体で試してみて下さいね。
また、拒否が強いご利用者様の対応については、施設のみならず、訪問介護での入浴、在宅で介護を行っているご家族様等、苦労されていることと思います。
足浴を行うだけでも爽快感は得られます。浴槽に浸かるだけなら拒否がない方もいらっしゃいます。単にお風呂を面倒に感じている方もいらっしゃいます。

可能であれば、洗顔・洗髪し、全身をくまなく洗浄し、浴槽に浸かっていただくのが一番ですが、全てをやらなければいけないと思わず、少しずつ進めて下さいね。
今回の記事は以上でございます。最後までお読み頂き誠にありがとうございました。


新型コロナウイルス感染拡大防止について
新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が5月14日に解除されて、ようやく少しずつ元の生活にと思っていました。
昨日、7月23日現在、東京都では、新たな感染者が366人、国内感染者981人と、過去最多となってしまいました。
高齢者様に直接関わる介護施設で働く私としては、感染しないよう対策はしています。
しかしながら、東京都の新規感染366人の6割以上も感染経路が解っていない状況下、どこかで感染しているのではないか、ご利用者様に移してしまうのではないかと不安は募るばかりです。
GoToキャンペーンより、緊急事態宣言の再発令が必要なのではないのでしょうか。
記事タイトルには直接関連していませんが、福祉・介護や医療に関わるお仕事に就かれている方にとって、新型コロナウイルスに関する情報に、私と同じように敏感になっているのではないでしょうか。一刻も早い事態の収束を願うばかりです。