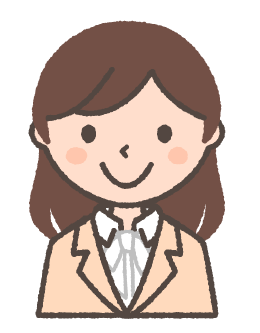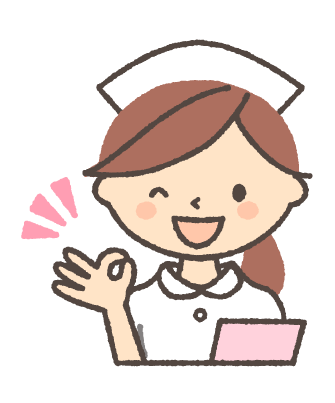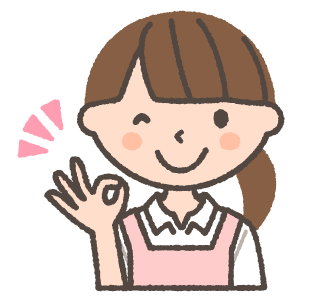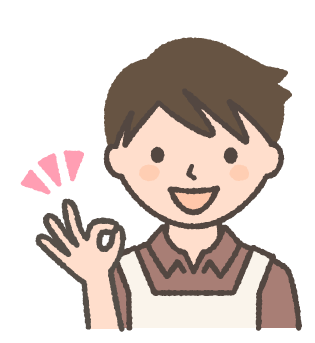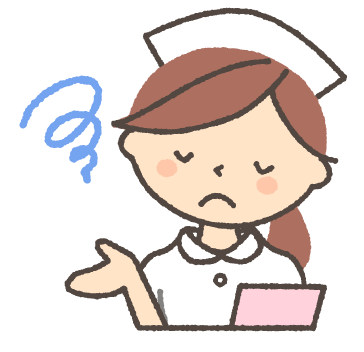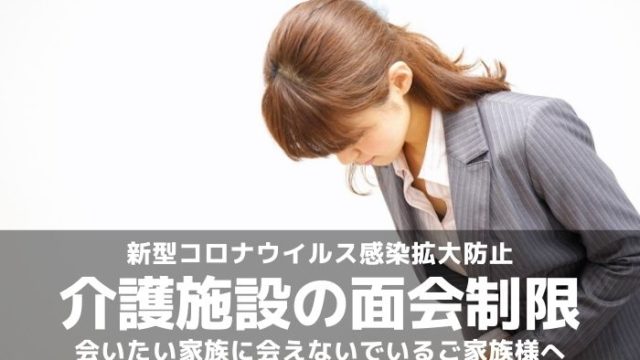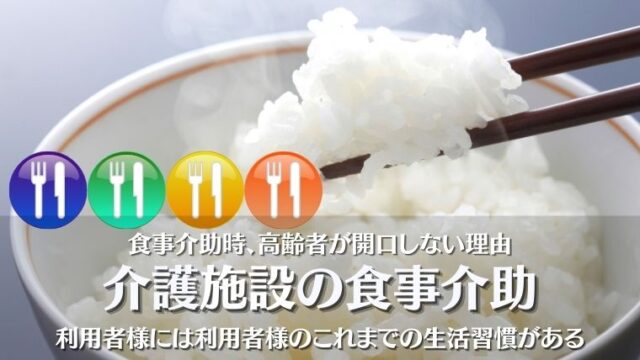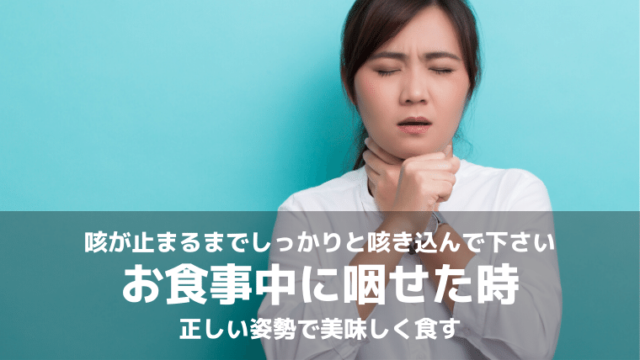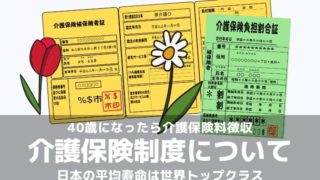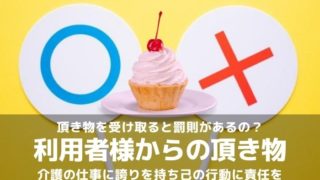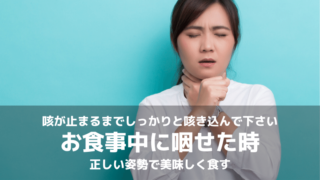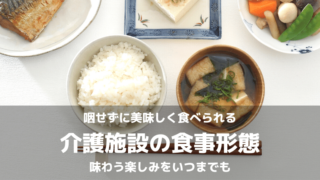6月に入って蒸し暑くなってきましたね。外出時のマスク装着で、既にバテ気味のめぐろでございます。めぐろの介護新聞にお越し頂きありがとうございます♡
前回は、事故報告書を作成する必要性についてを記事にしましたが、今回は、「ヒヤリハット報告書」についてを記事にします。実際にめぐろが作成した報告書見本も宜しければ参考程度にご覧下さいね(*^-^*)
大変失礼いたしました。では、早速本題に移りますね。宜しくお願い致します。
- ヒヤリハット報告書とは?
- 事故を起こしてもいないのに何故報告書が必要?
- ヒヤリハット報告書はたくさん提出した方が良いのは何故?
このような疑問をひとつずつ解説していきます
ヒヤリハット報告の重要性
ヒヤリハット報告とは、介護のお仕事を行う中で「ヒヤッ」としたり、「ハッ」としたりした際に作成する報告書です。偶然にも事故にはなりませんでしたが、次回は介護事故に至る可能性があります。内容を施設全体で周知することで、次に対応する職員はヒヤリハット報告書を基に、注意点を意識しながら対応することが出来ます。
ヒヤリハットの先には介護事故が控えている
ご利用者様の行動や、職員が行った行為から、「危険」と感じた時に作成する書類なのですが、「危険」と感じた先には、大きな事故が控えています。


ヒヤリハット内容から原因と改善策を導き事故防止に繋げよう
ひとつ間違えると介護事故に至っていましたが、紙一重で職員の気付きから、事故を回避した時に、ヒヤリハット報告書を作成します。このヒヤリハット報告は、実は病院や施設にとって、とても大切な報告になります。先ず、解りやすくお伝えする為に、ひとつの例を挙げて説明させていただきますね。
ヒヤリハット報告書を基に原因と改善策を考える
(介護施設の多くは、日中、ホールや食堂でお食事をとりますので、食後のお薬はお食事席で内服します。一方、「寝る前」のお薬は20時頃、各お部屋に訪室して服薬介助を行うことになります。)
いつものように、A様のお部屋に伺い、就寝時薬を内服して頂くお声かけを行いましたが、既にA様はうとうとされていました。
お薬をきちんと内服して頂くために、A様と少し対話を行い、しっかりと目が覚めたことを確認してから寝る前のお薬2錠を飲んで頂きました。
内服確認後、A様のお部屋から出て、お薬の袋が空であることを確認してホッとした職員ですが、内服時に使用したお水が入っていた湯飲みを洗おうとした際、2錠のうちの1錠がコップの底にくっついていました。
急いで、再度、A様のお部屋に伺い、飲めていなかったことを説明して、もう1錠を飲んで頂きました。
上記は「ヒヤリハット報告」が必要な内容です。お水を入れていた湯飲みの中にお薬が残っている事に気付いた時、まさしく「ヒヤッ」としたと思います。
医師から処方されたお薬を決められた時間に内服できなかった場合は「ヒヤリハット報告」ではなく「介護事故報告(誤薬事故)」になります。
うとうとされているA様に、そのまま服薬介助を行うと誤嚥のリスクがあります。その為、職員はA様と数分間、雑談をして、覚醒状態(しっかりと目が覚めているか)を確認しています。
また、服薬後に、袋の中にお薬が残っていないかの確認も行っていました。しかしながら、実際は、内服しなければならない2錠のうちの1錠しか飲めていませんでした。
このヒヤリハットの先には「誤薬(ごやく)」という事故が控えています。高齢者が医師から処方されるお薬で多いものとして、血圧に関するお薬だったり、血糖に関するお薬だったり、血流に関するお薬、下剤も多いです。
大切ではないお薬なんてありませんが、特に身体に直接影響する、とても大切なお薬ばかりです。飲み忘れる、飲み損ねることがないようにしなければなりません。

次に、今回のヒヤリハットから、気付いたこと、改善することを纏めていきます。
原因1:
既に眠そうにされていた為、居室の照明は点けなかった。
職員が眠前薬をお部屋にお持ちした際、A様は既にうとうとされていました。職員は、お薬だけ飲んで直ぐに休んでいただこうと、居室の照明は点けませんでした。
改善策:
眠前薬内服時は、お部屋の照明は必ず点けて内服の確認を行うこととした。
原因2:
寝る前のお薬をお持ちした際、既にうとうとされていた。
職員が、A様の居室にお薬をお持ちしたのは20時少しまわったところでした。その時間、A様はいつもうとうとされていたり、眠っていることもありました。
眠っている方を起こして「眠前薬」を飲んで頂くこと自体がそもそもおかしいですね。
改善策:
就寝前薬の内服時間の変更を医師に相談し、19時に内服することとなった。
原因3:
お薬と一緒にお持ちしたお水が入った湯飲みに問題があった。
施設内の全フロアで使用しているお薬用の湯飲みは、内側が白色のものでした。お薬の色は殆どが白色です。A様は、口腔内に入ったお薬を飲み込もうと、お水を口にふくむ際に、口の中に入っていたお薬が湯飲みの中に、こぼれ落ちたことが推測できます。
改善策:
全フロアのお薬用の湯飲みを、透明のコップに変更した。
原因4:
2錠のお薬を1度に口腔内に入れた為、A様は飲み込みづらかった。
朝食、昼食、夕食後のお薬を飲んで頂く際、眠前薬に比べると割りとスムーズに内服できますが、眠前薬はベッド上での内服となり、日中と比べ、飲み込みが悪くなることを考慮しましょう。
改善策:
お薬は1錠ずつ確実に飲んで頂くこととした。
原因5:
眠前薬を内服時、ベッドの頭部を挙上(電動ベッドの頭部側を上げる)して行っていた。
高齢者はもともとが若い頃に比べ、飲み込む機能が低下傾向にあります。(嚥下機能低下)甘いもの等、好きなものは比較的スムーズに飲み込めますが、お薬に美味しいものはなく、苦い、まずいイメージが強く、それだけでも飲み込みは悪い状態にあります。
改善策:
ベッドから足を下ろして端座位で服薬介助を行う。(食事と同様に両足底は床に付ける)
今回は原因を5つ抽出しましたが、たくさんの職員で話し合えば、もっと多くの原因が挙がると思います。では5つの改善策を考慮したA様に対する眠前薬の服薬介助を行ってみましょう。

改善策を基に、服薬介助を行ってみよう
改善策を取り入れ眠前薬介助を行いましょう
眠前薬を内服して頂くために、19時にA様のお部屋に訪室しました。A様はベッドに臥床(がしょう・横になる)されていましたが、テレビを視聴されていました。居室の照明は点いていました。
職員が寝る前のお薬をお持ちしたことをお伝えし、ベッドに端座位になって頂けるようお声かけをして(※端座位とは、ベッドから体を起こし、足を下ろして座る。)足底が床に付くようにベッドの高さ調整を行います。
透明コップに入ったお水と2錠あるお薬の1錠をA様の手の平に乗せ、内服の確認を行い、続いて2錠目を同様に内服確認しました。
更に、薬の袋内にお薬が残っていないかを確認しました。服薬介助後、ベッドに臥床介助を行い退室します。
ヒヤリハット報告は全職員に周知を
ヒヤリハット報告は、ユニットやフロアだけではなく、施設全体に周知が必要です。
他のフロアであったヒヤリハットは自分の担当するフロアでもあり得ること
おそらくA様は次の巡視時間の20時には、既にうとうとされている、若しくは入眠されていることが予測できます。19時に眠前薬は内服されていますので、例え眠られていてもわざわざ入眠されているA様を起こす必要がなく、今回のヒヤリハット報告は、事故防止策の他にも、ケアの改善ができたということになります。
また、今回のヒヤリハット報告を全職員が周知することで、眠前薬の内服介助を行う際、あらかじめ留意点が解っているので、事故防止に役立ちます。
口腔内に入ったお薬が、水を含む際に口腔内からこぼれ落ち、コップの中に残っている可能性がある。更に、コップ内に落ちることなく、コップ以外の場所(ベッド上、衣類、床等)に落ちるかも知れないという注意力が増します。
A様に限らず、薄暗い居室内での服薬介助は、お薬の飲み損ないや、落薬となるリスクがあるため、眠前薬内服時は、ご利用者様に理由をお伝えして照明を点けさせて頂きましょう。明るい場所で服薬することは、職員の確認がしやすいだけではなく、ご利用者様も手の平に乗せた薬がきちんと飲めたか、落としたかが解りやすくなります。

ヒヤリハット報告はたくさんあるほど事故は減る
ヒヤリハット報告が多い施設は事故が少ないです。そもそも介護を行う上、ヒヤッとしたりハッとしたことがない人はいらっしゃらないと思います。
ヒヤッとした場面をこれまでの私の経験から挙げてみます。
業務を行う中で、同じようなヒヤッとした経験があるのではないでしょうか。隠れている事故の7~8割りが「転倒・転落」です。
| ヒヤッとしたりハッとした内容 | 隠れている事故 |
| 部分入れ歯を外して咀嚼していた | 誤飲 |
| 食後、入れ歯をティッシュで包んでいた | 紛失 |
| 食事を間違えて配膳しそうになった | 誤嚥 |
| 利用者様が他の方の食事に手を伸ばした | 誤嚥 |
| 歩行付き添い時、利用者様が滑ってバランスを崩した | 転倒・骨折 |
| 入浴前、お湯をかき混ぜたら熱かった | 火傷 |
| 入浴中、急に呼吸が早くなった | 急変 |
| 下剤の反応便が多量に出た際、反応が悪くなった | 急変 |
| 車椅子⇔ベッドへ移乗時、支えきれず転びそうになった | 転倒・骨折 |
| 車椅子から立ち上がり歩き出した | 転倒・骨折 |
| 巡視時、ベッドから落ちそうになっていた | 転倒・骨折 |
| 他の方の薬を飲ませてしまうところだった | 誤薬 |
| 一週間に一度の薬を忘れてしまいそうになった | 誤薬・飲み忘れ |
ヒヤリハット報告書が作成しやすい環境を整えよう
介護(看護)業務を行う中で、本来ならヒヤリハット報告が必要な場面に遭遇して、尚且つ「ヒヤリハットが起きた」ことに気付いていても、書類を作成することが面倒で報告を怠ったことはありませんか?
「ヒヤリが起きた。あとで書かなきゃ」と思っていたのに、終業時には忘れて帰宅してしまったり、忘れて帰宅したことを思い出しても「もういいか」と勝手な考えで報告書の提出を怠る行為を、明日から改めましょう。
報告書を提出しない理由
業務中は、書いている時間が中々とれないと思います。そのため、どうしても業務終了後になってしまうことが多いです。新人職員の場合は、30分程度は書類作成に時間が掛かるのではないでしょうか。
では、終業後、ヒヤリハット報告書の作成をする場合、その30分は残業として扱ってもらえるかという点です。
本日の記事にも書きましたが、ヒヤリハット報告書とは、大事故を回避するための大切な気付きを書類にするという作業です。
実際の介護(看護)業務も大切ですが、それと同じように書類の作成も大切です。その気付きレポートは、実は、ご利用者様に安全にお過ごし頂く為のものであるということです。
ご利用者様だけではなく、職員にも安全な介護(看護)を行う為の導きであり、業務の効率化、改善です。
書類を作成しやすい環境を作るために
私が働いている介護施設は、ヒヤリハット報告書のみならず、介護事故報告書の作成を行う際は、残業手当が30分付きます。
また、書式も書きやすいものに変えています。あれこれと細か過ぎる書式は、「書きたい」気持ちを失います。一度でも、書いたことがある方なら解りますよね。
施設全体会議や事故防止委員会(リスクマネジメント委員会)若しくは、ユニット、フロア会議等の議題に挙げて、事故報告書、ヒヤリハット報告書を書く必要性、書類の書きやすさ、更に業務として認めて下さるよう(サービス残業をなくす)訴えるというと角が立つので、話し合いの場を設けてみてはいかがでしょうか。
介護職に携わっている職員の全てが、ヒヤリハット報告を行うことが何故大切なのかを、もしかしたら知らない、忘れている方もいるかも知れません。
私達、介護を行う人の意識の持ち方が、ご利用者様に痛い思いや辛い思いをさせないことに繋がっています。
この記事の終わりに・ヒヤリハット報告書の書き方
ヒヤリハット報告書の大切さについてを記事にしましたが、いかがでしたでしょうか。
他職員が書いたヒヤリハット報告書を見ると、「こういう方法はどうか」「これも加えてはどうか」等、次々とひらめくことも多いです。
今回使用した書式は、かなり細かめになっています。ヒヤリハットの内容を理解して頂きたく、この書式を使用しましたが、もっと書きやすいものが良いですね。
是非、この記事の終わりに、めぐろが書いたヒヤリハット報告書を見て頂き、ひらめきや、新たな気付きを生む練習をしていただけると幸いです。
また、冷やかしたいたろう君が出てきそうなので、わたくしめぐろはこれで失礼致します(笑)最後まで読んで下さいまして、誠にありがとうございました。
作:めぐろが書いたヒヤリハット報告書(書き方見本)はこちらから